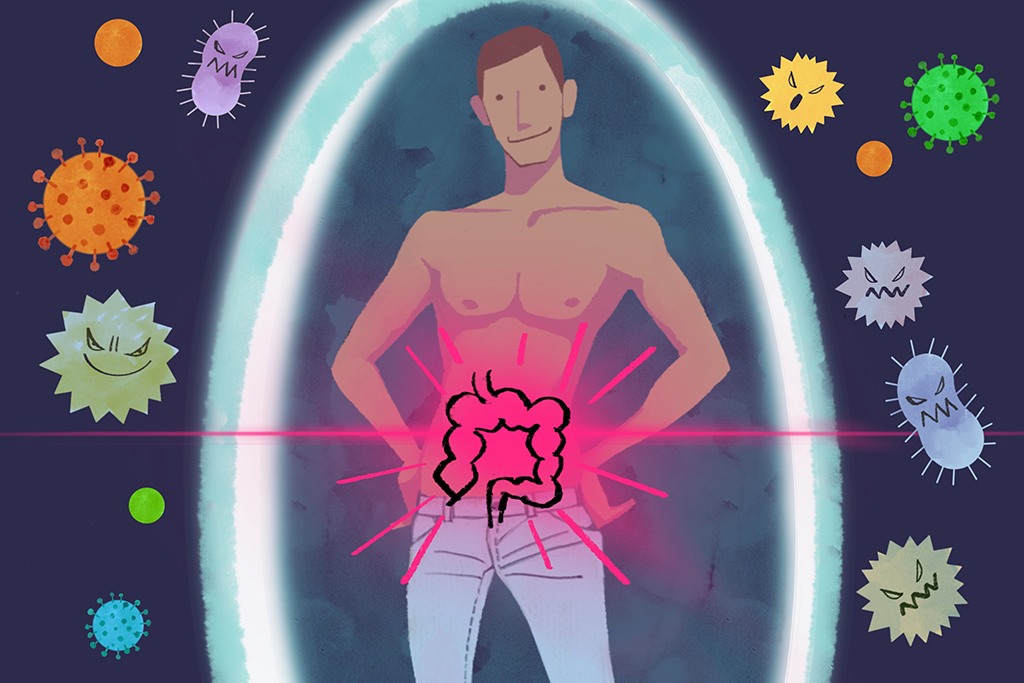- 1月の特集テーマ
- 神社仏閣をめぐる旅。
仏像さまのご利益と、その魅力
2018.01.15仏像は信仰の対象として造られたものです。仏様はさまざまな性質や働きを持っておられ、次第に人の願いを叶えてくれる存在として拝まれるようになりました。今週の「きのこで菌活。」コラムでは、食事で叶える代謝を高める身体づくりをご紹介していますが、「トレンドコラム」では、人々の願いを叶えると言われてきた仏様のご利益について紐解きます。
仏像は信仰の対象として造られたものです。仏様はさまざまな性質や働きを持っておられ、次第に人の願いを叶えてくれる存在として拝まれるようになりました。今週の「きのこで菌活。」コラムでは、食事で叶える代謝を高める身体づくりをご紹介していますが、「トレンドコラム」では、人々の願いを叶えると言われてきた仏様のご利益について紐解きます。

- 教えてくれたひと
吉田さらさ(Yoshida Sarasa)
岐阜県生まれ、早稲田大学第一文学部美術史学科にて東洋美術史と西洋美術史を学ぶ。大学時代に仏像の美しさに惹かれ、寺を旅する魅力に気づく。寺と神社をめぐるうちに、日本の仏教や神道の奥深さに惹かれ、現在は寺と神社の旅の専門家として、寺、神社、仏像、宿坊に関する単行本と雑誌記事を数多く執筆している。
仏像さまのご利益と、その魅力
「仏像は、手や指などの特徴、持ち物、衣服などで見分けることができ、それぞれに働きや性質も異なるとされています。美術品として見れば、材質の違いや一体一体の表情やポーズの違いなどにも気づきます。多くのお寺や美術館を巡ってたくさんの仏像を拝むことにより、特に自分の好きな仏像さまを見つけることができると思います」
仏像は、如来、菩薩、明王、天の4つのカテゴリーに分けられ、その他に羅漢、仏弟子、高僧などの像もあります。それらは厳密には仏ではなく人間の像なので、4つのカテゴリーとは別の存在ですが、一般的には、それらも仏像の一種に含めます。
如来は4つのカテゴリーの中の最高位で、すでに悟りを開いている存在。釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来など、読者の皆様もご存知の仏様が多いのではないでしょうか。
「仏像さまにはそれぞれの専門分野があり、叶えてくれる願いごとが違うということをご存知ですか。阿弥陀如来は極楽浄土専門の如来様。南無阿弥陀仏という念仏を唱えれば、死後、極楽浄土に連れて行ってくださると言われています。また、薬師様は病気平癒の願いを叶えてくださる如来様です。わたしは、体調が悪い時や、家族や友人が病気の時、よくこの薬師如来様にお参りします」
また、菩薩は悟りに至る一歩前の修行中の存在で、如来の補佐役とも言われ、観音菩薩、弥勒菩薩、文殊菩薩などが有名。文殊菩薩は『三人よれば文殊の知恵』という言葉があるように、知恵の仏様として、学業向上や合格祈願のためにお参りする人が多いです。
今回、仏様のお姿の特徴とその功徳について下記のようにまとめました。功徳とは、その仏様にお参りすると、このようなよいことが起きるというという意味で、簡単に言えば、「ご利益」のことです。仏様によって、功徳は千差万別です。
■ 如来 ■
すでに悟りを開いた存在で、4つのカテゴリーの中では最高位。釈迦如来の姿が基本。
質素な衣を身に着け、基本的に装身具はつけない。(大日如来を除く)

| 釈迦如来 | 仏教の開祖であるお釈迦様の姿をモデルにした像で、すべての如来像の基本となる。人を悟りへと導いてくれる。 |
|---|---|
| 薬師如来 | 病気平癒の願いを叶えてくれる仏様。手に薬を入れる壺を持っている。日光菩薩、月光菩薩を両脇に従えていることが多い。 |
| 阿弥陀如来 | 亡くなった人を極楽に迎え入れてくれる。人の徳の段階を示すいろいろな手の形があるが、共通点は指で輪を作っていること。 |
| 大日如来 | 密教の世界の最高位の如来で宇宙の中心。他の如来は装身具をつけないが、大日如来だけは冠やネックレスをつけている。 |
■ 菩薩 ■
悟りに至るひとつ手前の存在で、如来の補佐をする役割を持つ。
もとはインドの王子であった釈迦如来の姿を表すとも言われ、冠やアクセサリーを身につけている。

| 聖観音菩薩 | 観音様は人の願いを叶えるために様々な姿に変身するが、基本形はこの聖観音。頭がひとつ、手が二本の、人間と同じ姿をしている。 |
|---|---|
| 十一面観音菩薩 | 頭の上に十一の別の顔を持つ観音様。前の方は優しい顔、横には怒った顔、後ろには悪を笑い飛ばす顔がある。 |
| 千手観音菩薩 | 頭上の11の顔に加え、千本の手を持ち、多くの人を救う観音様。実際に千本の手がある場合もあるが、四十二本に省略されることが多い。 |
| 文殊菩薩 | 釈迦如来に仕える脇侍だが、単独で祀られることもある。知恵と学問の仏として知られる。獅子に乗っていることが多い。 |
| 普賢菩薩 | 文殊菩薩とともに釈迦如来の脇侍として祀られることがほとんどで、単独の像は少ない。女人を救済し、成仏を助けてくれる。象に乗っていることが多い。 |
| 地蔵菩薩 | 弥勒菩薩が降臨するまでの間、六道(人が死後に輪廻する六つの世界)で苦しむ人々を救済する役割を持つ。若いお坊さんの姿をしている。 |
| 弥勒菩薩 | 釈迦入滅後の56億7千万年後に降臨して人を救済する未来の仏。降臨以降は如来となり、弥勒如来と呼ばれる。 |
| 日光月光菩薩 | 薬師如来の脇侍としてアシスタント的な役割を持つ。薬師如来をお医者さんとすると、日勤の看護婦さん、夜勤の看護婦さんに例えられる。 |
■ 明王 ■
仏の世界に敵対する者を叱りつけてでも諭す役割を持つため、怒りの表情、勇壮なポーズなどが特徴。
不動明王以外の明王の髪の毛は逆立っていることが多い。

| 五大明王 | 不動明王から金剛夜叉明王(宗派によっては烏枢沙摩明王)までの五尊の明王。魔をねじ伏せ、災厄を遠ざける力が大きい。 |
|---|---|
| 不動明王 | 大日如来の化身とされる。煩悩を打ち砕き、浄化した願いごとを天に届ける。特徴は、お下げにした髪、剣と縄を持つ手、炎の形の光背など。 |
| 降三世明王 | 仏の教えに従わない人を、怒りの力で降伏させる。ヒンズー教の神であるシヴァ神とその奥さんを踏みつける印象的な姿。 |
| 軍荼利明王 | 疫病や災厄をもたらす神を調伏する。額には第3の目があり、8本の手を持つ。体には蛇が巻きついている。 |
| 大威徳明王 | 6つの顔、6本の手足を持ち、水牛に乗っている。たくさんの手足は、より力が強いことを表し、戦勝祈願の仏として信仰された。 |
| 金剛夜叉明王 | 3つの顔があり、真ん中の大きな顔には目が5つある。手は6本あり、それぞれ武器を持っている。敵をねじ伏せる力が強い。 |
| 烏枢沙摩明王 | 煩悩や不浄を焼き尽くし、清浄にしてくれる。禅宗の寺などでは、トイレの守護仏として祀られることが多い。 |
■ 天 ■
古代インドの神話の神々が仏教に取り入れられたもの。
したがって、さまざまな姿や性質があるが、大黒天、弁財天など、名前に「天」がついていることが多い。

| 梵天 | もとは古代インドの宇宙を創造した神、ブラフマン。仏教に取り入れられ、仏の世界の守護神の一尊となった。ガチョウに乗った像が有名だが立像もある。 |
|---|---|
| 帝釈天 | もとは古代インドのインドラという神で、仏教の守護神として梵天とともに祀られることが多い。象に乗った像が有名だが立像もある。 |
| 毘沙門天 | 四天王の一員として北方を守る役目を持つ。戦勝、商売繁盛のご利益もあるとされ、単独でも信仰される。 |
| 吉祥天 | 毘沙門天の奥さん。もとは、幸運、美、財宝などを司るインドの女神、ラクシュミー。よい伴侶を得て幸せになりたい女性はぜひお参りを。 |
| 大黒天 | もとはインド神話の暗黒を司る神だが、日本に伝来して大国主命と同一のものと見なされたため、米俵に乗り、打ち出の小槌を持つ福の神として信仰された。 |
吉田さんが、そのお姿を見ると癒やされると言うのは、京都戒光寺にある、とても大きな仏像「丈六釈迦如来」なのだそう。戒光寺については、次週改めてご紹介致します。
新たなるご利益をもった観音様
それぞれの仏像さまには、経典などに書かれている古くから決まった功徳がありますが、その姿形や言い伝えなどから、後世に、また違うご利益があると考えられるようになり、庶民に信仰されてきた仏像もあるのだそうです。
「たとえば、『楊貴妃観音』と呼ばれる観音様があります。お姿が美しいのと、中国伝来の像であるため、後世に楊貴妃という通称名がつき、さらには、美しくなりたいという女性の願いを叶えてくれると言われるようになりました。ほかにも、おなかが膨らんで見えるために、『子授け、安産のご利益がある』と言われるようになった『腹帯観音』などもあります」

このように、今も昔も仏像さまが叶えてくれる願いはさまざまです。寺社を訪れる際には、その寺院のことを調べ、そこにどんな仏様が祀られているかを知ってから訪ねることで、参詣がより意味深いものになるのですね。
【1月22日更新の次週は、吉田さんおすすめの、ぜひ行ってみたい神社仏閣をご紹介します。】
安らかで落ち着いた時間の流れる寺社で心の元気をいただき、身体の調子は美味しい食事から整えませんか。暦は大寒、寒い季節には身体を温めてくれるような食事が一番です。食事にきのこを取り入れて、代謝&体温&免疫力アップを目指しましょう。
今おすすめのきのこレシピ
-
きのことゴーヤのチャンプルー
紫外線が強い時期の美容メニューをご紹介!きのこには別名“美容ビタミン”と呼ばれるビタミンB2が豊富に含まれるため、美容ケアにオススメの食材。またゴーヤはコラーゲンの生成に関わるビタミンCが豊富なため効果を後押し♪きのこのうま味がゴーヤの苦みを和らげる、お子様にもおすすめの夏の一品です。
レシピを見る

 【今週更新!きのこで菌活。】
【今週更新!きのこで菌活。】